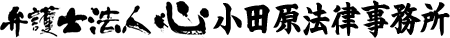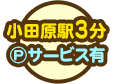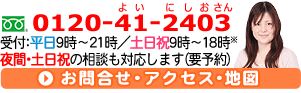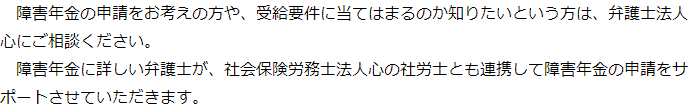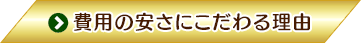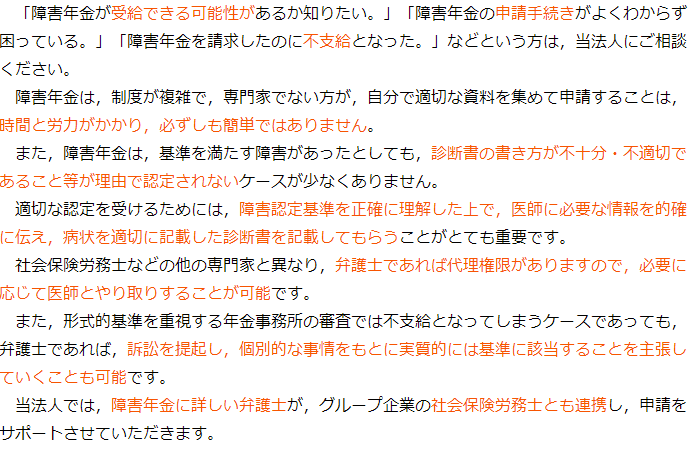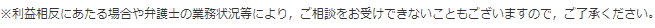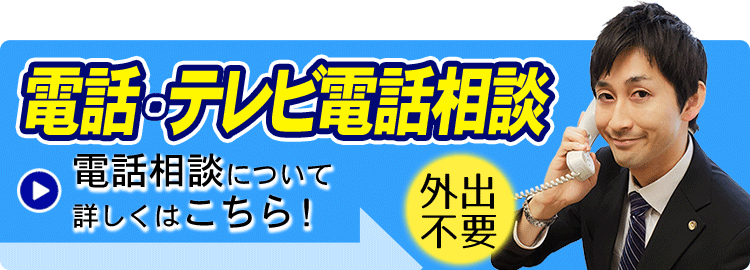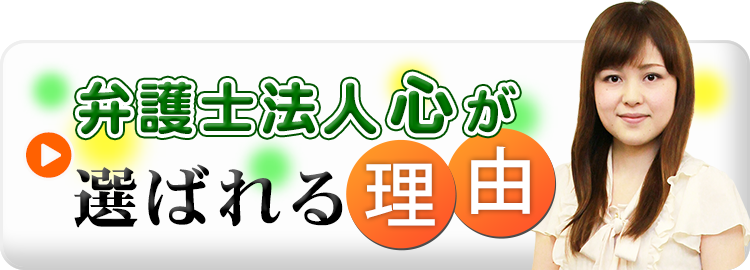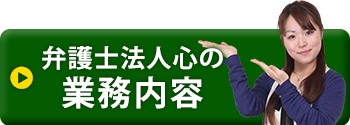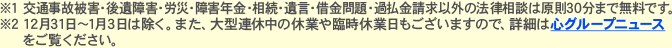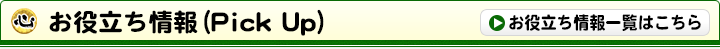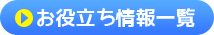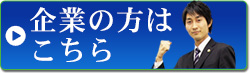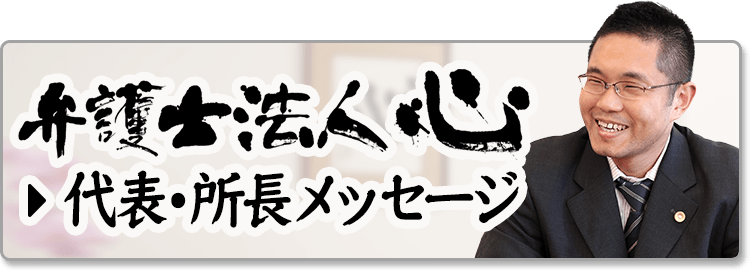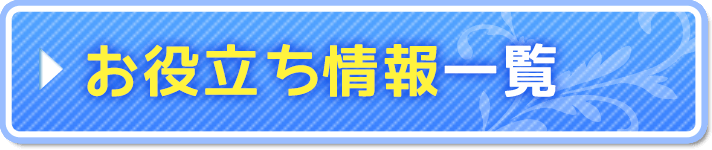障害年金
障害年金の受給資格
1 障害年金の受給資格
障害年金を受け取るためには、主に、初診日の要件を満たし、障害認定日以降の障害の状態が障害認定基準に該当し、初診日の前日に保険料納付要件を満たしている必要があります。
では、具体的には、どのような要件を満たしている必要があるのでしょうか。
2 初診日の要件

障害年金の初診日は、障害の原因となった病気やけがの症状で初めて医師の診察を受けた日をいいます。
障害年金を受け取るためには、初診日が、①国民年金または厚生年金の加入期間、または、②20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上または65歳未満で年金制度に加入していない期間、であることが必要です。
初診日は、確定診断を受けた日ではなく、障害に関連する症状で診察を受けた日です。
例えば、うつ病の場合でも当初は食欲不振で内科で診察を受けていれば、内科で診察を受けた日が初診日になることもあります。
障害年金申請の際には、確定診断を受けるまで色々な病院を転々としていることや、症状が悪化して障害状態になるまでに時間が経っていることもあります。
病院が廃院になっていたりカルテが廃棄されていいたりするなどして、そもそも初診日を確定して初診日を証明することが難しいことがあります。
初診日の証明ができれば、日本年金機構から年金記録を取り寄せれば年金保険に加入していたかどうかははっきりします。
3 障害認定日以降の障害の状態
障害年金を受け取るためには、障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める一定の要件に該当していることが必要です。
障害の状態は、医師が作成した診断書や、本人が作成した病歴・就労状況等申立書の内容をもとにして、障害認定基準に基づいて審査がされます。
障害基礎年金には障害等級1級と2級があり、障害厚生年金には障害等級1級と2級に加え、3級や障害手当金(一時金)の制度があります。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級1級と2級の障害認定基準は同じですので、障害厚生年金のほうが手厚い保障といえます。
4 保険料納付の要件
障害年金を受け取るためには、原則として、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること必要です。
ただし、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっていますし、年金制度に加入していない20歳前の期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
年金保険料の納付が困難な場合には、年金保険料の免除や猶予の手続きをして承認されていれば未納になりませんので、年金保険料を納めていた期間とみなされて納付要件を満たしていることになります。
障害年金の場合も初診日の前日までに手続きができていればその期間の年金保険料は未納になりませんので、障害年金の受給資格を守るためには必ず期限内に必要な手続きをしておきましょう。
障害年金の受給資格
1 障害年金と所得による制限
障害年金を受給するにあたって、収入額による影響はあるのでしょうか。
この記事では、申請の種類による違い等についてご説明いたします。
2 通常の申請について所得制限はありません。

基本となる障害基礎年金の申請、障害厚生年金の申請に関しては、所得による制限はありません。
そのため、20歳以降に初診日のある障害年金申請については、高収入だからという理由をもって障害年金の申請が認められないということはありません。
ただ、難病や精神疾患等、抽象的な障害認定基準となっている類型の審査にあたっては、事実上の審査結果に影響が出ることは考えられます。
障害年金認定基準の基本的事項によれば、障害厚生年金3級については、「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。」と規定されています。
著しい就労制限を受けながら高収入を得ることは容易ではないため、審査する側としては、高収入である=労働にあたって「著しい制限」があるとまでは言い難い=障害年金の対象となる傷病の水準ではないという判断に結びついていきます。
3 20歳前障害基礎年金には所得制限がある
20歳前障害基礎年金というのは、初診日が20歳以前の場合の障害年金申請です。
障害年金も、原則65歳から受給が始まる老齢年金と同じ年金制度の1つで、基本的には保険料の納付が前提となっています。
しかし、初診日が20歳以前の場合、まだ保険料の納付義務がないため、結果として保険料の納付がなくても障害基礎年金の受給が認められる場合があります。
保険料を納めなくても年金が受給できてしまう、ということとの均衡から、一定の所得を得られている方の場合には、年金の受給に制限がかけられています。
4 具体的な制限内容
詳細については日本年金機構のページに掲載されています。
参考リンク:日本年金機構・20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等
おおまかにまとめると、前年の所得額を基準に、370万4000以下であれば全額支給(=制限なし)、472万1000以下までは1/2の支給停止、それを超える場合には全額停止となり、受給が認められないということになります。
対象期間の基準は、10月から翌年9月までとなっております。