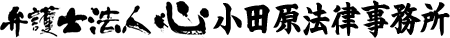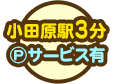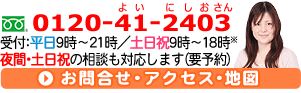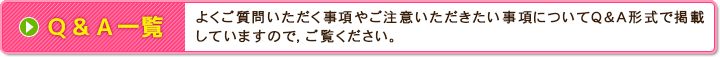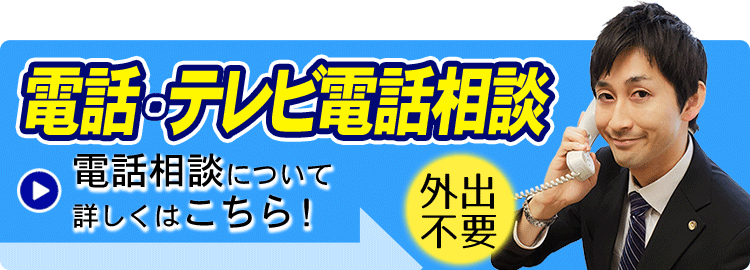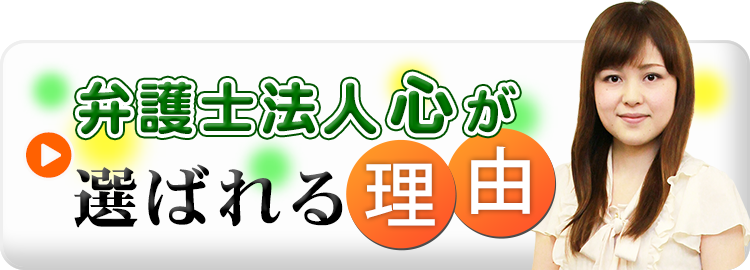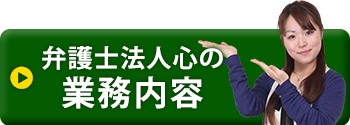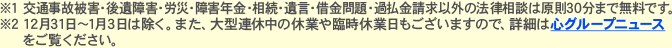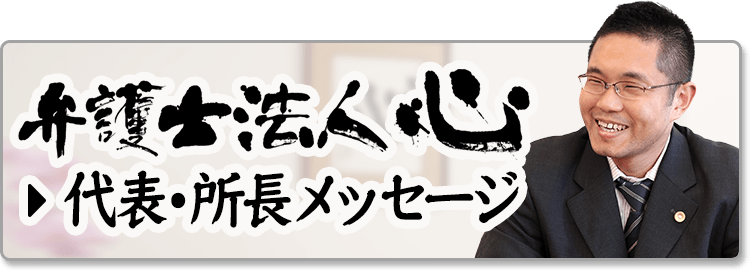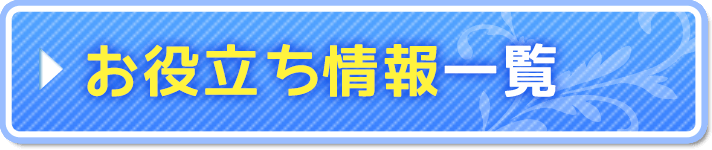相続手続きで間違いやすい注意点
1 相続手続きの前提として行わなければならない作業があります
相続手続きというと、まずは銀行口座の解約や不動産の名義変更を思い浮かべる方も多いと思います。
しかし、実際には、これらの手続きの前に行わなければないことがあります。
具体的には、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成です。
まず、相続人調査をするためには、基本的には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を収集します。
この後に行う遺産分割協議は、相続人全員で行わないと無効になってしまうため、相続人の調査はとても重要な作業になります。
相続人と並行して、被相続人の財産や負債を正確に把握する相続財産調査を進めます。
相続財産調査に抜け漏れがあると、遺産分割協議を複数回行わなければならなくなることや、相続税の申告漏れを起こす可能性があります。
その後、誰がどの財産を取得するかを決める遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、多くの相続手続きで使用される資料になります。
2 相続登記には期限がある
令和6年4月に、不動産の相続登記が義務化されました。
基本的には、相続が発生し、被相続人の不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく期限内の相続登記を怠った場合、10万円の過料10万円が科される可能性があります。
3 納税額が0円でも相続税申告が必要な場合がある
相続税の申告は、基本的には相続財産の評価額が基礎控除額(=3000万円+600万円×法定相続人数)を上回り、納付すべき相続税が発生する場合に必要とされます。
しかし、実は納税額が0円であっても申告が必要となるケースがあります。
代表的なものとして、配偶者控除と小規模宅地等の特例を利用する場合が挙げられます。
被相続人の配偶者には、大幅な相続税減額制度が設けられているため、被相続人が相続財産をすべて取得した場合には納税額が0円になることもあります。
小規模宅地等の特例を用いると、被相続人の自宅や事業用の敷地の評価額が大幅に下がり、相続財産全体の評価額が基礎控除額を下回ることもあります。
これらの制度の適用を受けるためには、必ず相続税申告が必要です。
申告をしなければ特例が使えず、本来支払わなくてもよい相続税を支払わなければならなくなる可能性があります。