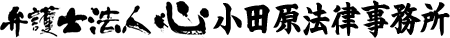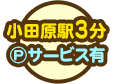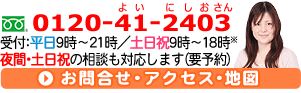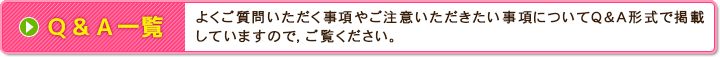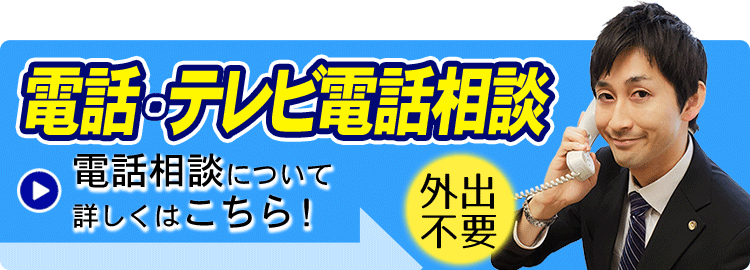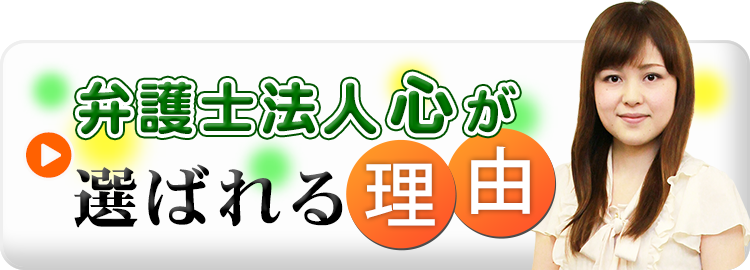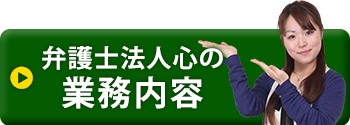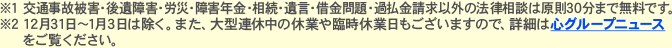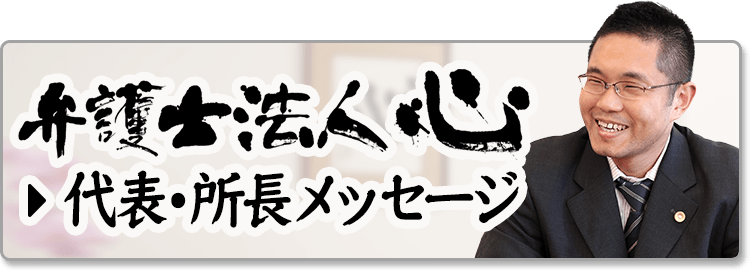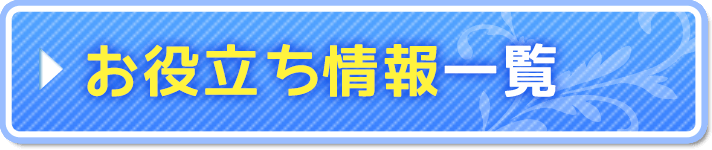死亡した人の口座をそのまま使うことの問題点
1 被相続人の口座は原則として相続手続きをしなければならない
人が亡くなると、基本的にその人(被相続人)の財産(預貯金、不動産、株式など)はすべて相続財産となり、相続人が取得することになります。
金融機関等においては、通常であれば相続の開始(被相続人の死亡)が確認された時点で被相続人の口座を凍結するため、その後の預貯金の引き出しや送金等はできなくなります。
これは、遺産分割協議が確定するまでに、預貯金が不正に流出することを防ぐための措置です。
凍結された口座の解約、預貯金の払戻しするためには、基本的には相続人全員による遺産分割協議を終え、遺産分割協議書や戸籍謄本等の提出が必要になります。
相続が発生した場合には、法律で認められた例外を除き、遺産分割協議前には被相続人の預貯金は利用できないことを前提とするべきです。
2 民事上の問題点について
被相続人の口座に入っている預貯金は、遺産分割協議前は相続人の共有財産になります。
他の相続人の同意や遺産分割協議なしに被相続人の預貯金を使うと、民法上返還する責任が生じる可能性があります。
例えば、一部の相続人が遺産分割協議や銀行での相続手続きを経ずに被相続人の口座から預貯金を引き出した場合、他の相続人からすると、共有である相続財産を使い込まれたように見えます。
そのため、引き出した額の返還を求められることがあります。
遺産分割協議の段階で引き出した預金を相続財産に組み戻し、改めて話し合いをして取り分を決められれば、事実上は問題が生じにくいと考えられます。
もっとも、勝手に引き出したことにより、相続人間での信頼関係が崩れ、遺産分割協議が難航する原因になることも少なくありません。
相続放棄をお考えの方へ 不倫慰謝料を分割で支払うことはできるか